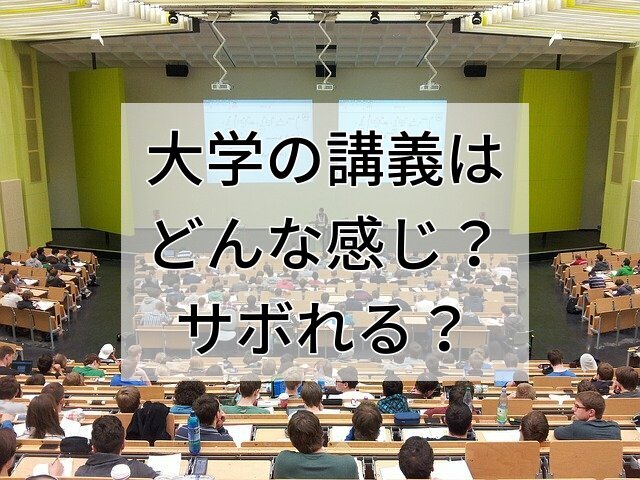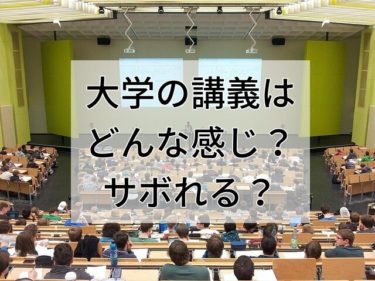大学の講義がどんな感じか気になる人「大学の講義ってどんな感じなんだろう?どんな形式で行なって、どのくらいの人数で、どんな風に成績がつけられるんだろう?あと、休むとどうなるのかな?サボることはできるのかな?」
このような疑問に答えていきます。
★本記事の内容
- 大学の講義はどんな感じ?
- 大学の講義を休むとどうなる?
- 大学の講義はサボることは可能?
こんにちは、Daisukeです。
みなさんの大学の講義のイメージはどんなものでしょうか?
映画、ドラマでよく見るめっちゃ広い教室の1番前で教授が一人で授業をしていて、それを生徒がノートにまとめている。
もしくは、話を聞かずに友達としゃべっている。
そんなイメージを持っている人が多いのではないでしょうか?
そのイメージはほぼ合っています。
この記事では現役大学生の僕が、そのイメージにさらにどのくらいの人数でどのように成績がつけられるのか、授業時間はどのくらいなのかなど、具体的なものにしていきます。
また、講義を休むとどうなるのか?
このようなことを説明していきます。
そして最後に、僕や僕の友達が実際に行なっていた講義をサボる方法を伝授していきます。
大学の講義形式はどんな感じ?

大学の講義形式は大学によって少しづつ違うと思いますが、どこの大学でも共通して言えるであろうことを解説していきます。
大学の講義は基本的に2つの形式があります。
そして最近増えた1つの形式があります。
★大学の講義形式
- 講義をただ聞いているだけ形式
- 生徒参加形式
- オンライン形式
講義をただ聞いているだけ形式
1つ目が先生の行う講義をただひたすら聞いているだけの形式です。
おそらくみなさんがイメージする大学の講義はこの形式だと思います。
先生がひたすら教室の前で講義をして、生徒はひたすらノートを取るというものです。
ドラマや映画でそのような光景を見たことがあるかもしれません。
こちらの動画は、仙台白百合女子大学の模擬授業で本当の講義ではないですが、講義の形式としては、本当の大学の講義そのままで、皆さんのイメージする通りだと思います。
先生がひたすら前で講義をしていますよね。
この動画の教室の広さは、普通に大きいというレベルだと思います。
しかし、規模の大きい大学の講義で使われる教室は、この教室の2倍、3倍くらいあります。
そこまで大きい教室で講義を聞くと、おそらく高校では味わえない雰囲気を味わうことができます。
なので「大学生になったな」と感じることができるかもしれません。
こちらの動画は、実際の大学の講義になっています。
少し前の動画なので平成感の漂う服装をしていますが、そんなことよりも講義中とは思えない程うるさいですよね。
この動画の中でわかると思いますが、前の方に座っている生徒はしっかりと講義を聞いている感じがします。
しかし後ろの方に座っている生徒は基本、授業を受ける気がありません。
普通に友達と会話をしているし、ゲームをしているような人もいます。
これが大学の自由さというものだと思います。
ただあの動画内の講義は私語がうるさすぎると思います。
あれだけ騒がしくなっているのに何も注意をしない先生もどうかしていると思います。
あんな講義は一部の大学の一部の講義だけなので安心して大学に来てください。
生徒参加形式
2つ目は生徒参加形式です。
1つ目の形式は、ただ先生がひたすら講義をするだけでしたが、生徒参加形式は、言葉通り、生徒にも講義内で何かしらのアクションを起こしてもらうものです。
1番多いのが、先生が講義中に特定の生徒に質問を投げかけて、それに答えてもらうというものです。
この形式の講義は楽しいですが、興味のない講義の場合、自分の考えなど何もないので、いつ当てられるのかドキドキしてしまいます。
オンライン形式
最後の形式は、オンライン形式です。
こちらが最近増えた形式になります。
みなさんもご存知のように、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、一時期、大学に通えなくなった時期がありました。
現在、大学生以外の人も、もしかしたらコロナの影響で、オンライン授業を経験したことのある人もいるのではないでしょうか?
この記事を読んでいる人は、比較的若い年齢層だと思います。
なのでオンライン授業がどんな感じで行われているのか、大体想像がつくと思います。
ですが、一応説明しておきます。
まずオンライン授業を行うときには、講義を行うためのプラットフォームが必要になります。
★オンライン講義を行う際のプラットフォームの例
- Google Classroom
- Zoom
大体がこのどちらかを使ってオンラインで講義を行います。
もちろんこれ以外のプラットフォームを使う大学、もしくは教授がいるかもしれません。
しかし基本は、この2つだと思います。
Zoomは、皆さんご存知の人も多いと思います。
コロナを経験したことのある皆さんならば、使ったことのある人も多いのではないでしょうか?
授業の流れとしては、まず講義をしてくれる教授がZoomでルームを作成してくれます。
その後、その教授が作成したルームのURLがメールで送られてくるので、それをクリックします。
すると勝手に教授が作成した講義用のルームに飛ぶので参加するだけです。
たまに教授からURLのメールが送られてこない時もありますが、その時は慌てずに教授に連絡しましょう。
Google ClassroomもZoomとほとんど流れは、同じです。
ただ一つ違うのは、Google Classroomでは、Classroomのプラットフォーム内に、講義それぞれのグループが作られます。
そのグループに参加するためには、授業の履修登録後に、その授業の担当教授からグループに招待されます。
そして参加するだけです。
そのグループに講義用のルームのURLが送られるので、そこをクリックします。
するとZoomの時と同じように勝手にルームに移動してくれます。
Google Classroomのグループ内では、URLだけでなく、課題や出席フォームなども送られてくることもあります。
この課題が送られてきたり、出席フォームが設けられるかどうかは、担当教授次第なので、しっかりとオンライン授業1回目の講義での教授の説明をよく聞くようにしましょう。
そしてオンライン講義の中にも2つの形式があります。
★オンライン講義の形式
- ライブ形式
- オンデマンド形式
ライブ形式は、言葉の通り、リアルタイムで教授が講義をしてくれます。
一方、オンデマンド形式は、教授が先に撮影しておいた講義動画を授業時間になったら見るという形になっています。
どちらの形式になるかは、教授次第ですが、個人的にはリアルタイムの方が嬉しいです。
なぜならオンデマンド形式だと、緊張感がないし、YouTube動画を見ているのと変わらなくないですか?
高い学費を払っているのに、中田敦彦のYouTube大学を見てるのと変わらないのはおかしいです。
しかもその講義動画は、何年も同じ動画を使い回しているそうです。
そんなの嫌ですよね。
そもそもオンライン自体が嫌なのに。
大学の講義の人数はどんな感じ?

映画やドラマでは100くらいの大人数で講義を受けているというイメージがあるかもしれません。
もちろんそのような講義もありますが、ほとんどがもっと少ない人数で行われています。
少ない講義だと30人かもしくはもっと少ない人数の講義もあります。
その受講人数によって講義が行われる教室のサイズも変わってきます。
受講人数が少ないと高校の教室のような小さい部屋で行われます。
★大学の講義の人数はどんな感じ?
- 100人近い講義もあるし、30人以下の講義もある
大学の講義の成績評価制度はどんな感じ?
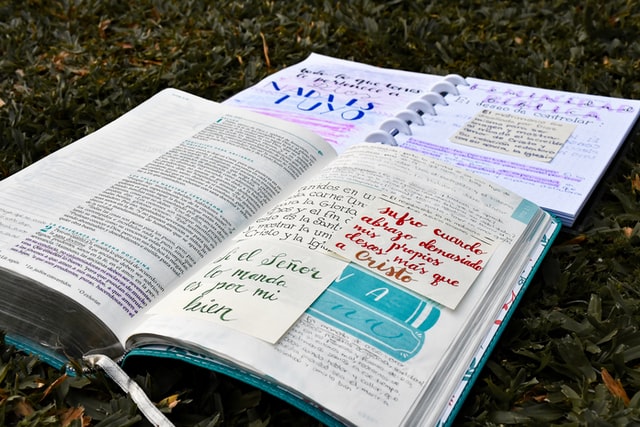
高校での成績評価制度は、5段階、もしくは10段階で評価されていたでしょう。
数字でなら、5、もしくは10が最高評価、1が最低評価でした。
この数字の合計が内申点と呼ばれるもので、大学受験を有利に進めるために、この内申点を稼ぐために必死になっていたことでしょう。
では大学の成績評価制度は、どんな感じになっているのでしょうか?
GPA制度
大学では、GPA制度が用いられています。
GPAとは、Grade Point Averageの頭文字をとった略です。
簡単にどういう制度なのかを説明します。
GPAとは、各授業の評価をそれぞれの段階に相当するGrade Pointに換算して、その合計を履修単位数で割ったものです。
つまり、全ての授業の成績の平均がGPAということになります。
なので1つの授業でめちゃくちゃいい評価をもらっても、もう1つの授業がめちゃくちゃ悪い評価だったら、プラマイ0ということになるわけです。
一度、GPA制度における評価やGrade Point、評価基準などを表にまとめてみます。
| 区分 | 評価 | 得点 | 評価基準 | Grade Point |
|---|---|---|---|---|
| 合格 | A+ | 100〜90点 | 到達目標を卓越した水準で達成している | 4.0 |
| 合格 | A | 89〜80点 | 到達目標を優れた水準で達成している | 3.0 |
| 合格 | B | 79〜70点 | 到達目標を良好な水準で達成している | 2.0 |
| 合格 | C | 69〜60点 | 到達目標を基本的な水準で達成している | 1.0 |
| 不合格 | D | 59〜0点 | 到達目標を達成していない | 0.0 |
| 試験欠席 | E | 試験欠席 | ー | 0.0 |
| 失格 | F | 失格 | ー | 0.0 |
評価が良ければ良いほど、Grade Pointも高くなり、その平均、つまりGPAも高くなります。
A+からCまでが単位がもらえる評価になります。
評価がDだと、いわゆる落単、単位を落とすことになります。
それ以降のEは、言うまでもなく試験を欠席するとEになります。
Fの失格というのは、後でまた説明しますが、出席回数が足りずに、そもそも試験を受ける資格がなかった、
もしくは、カンニングなどの不正行為などで失格になります。
GPAを自動で計算してくれるサイトもあるので気になる方は、こちらからどうぞ。
成績を気にする人にとっては、やはりA+を取りたいですよね。
では、A+の評価を得るためにはどうすればいいのでしょうか?
次で大学の講義の評価方法を解説していきます。
大学の講義の成績評価方法はどんな感じ?
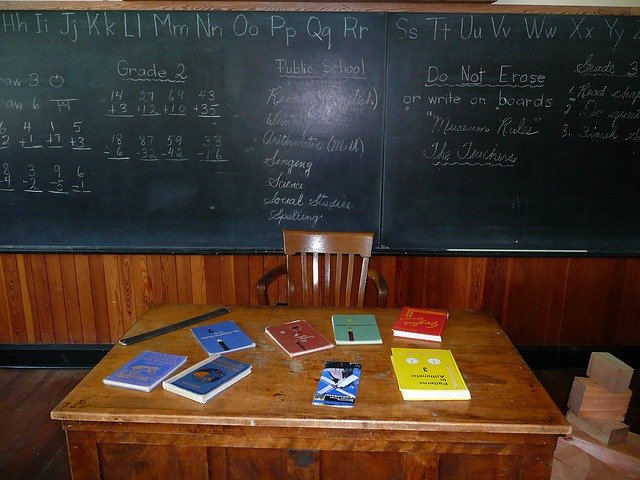
先ほど、A+などのように高い評価を得ることができれば、GPAが高くなると説明しましたが、どうすれば高い評価を得ることができるのでしょうか?
高校な場合は、定期テスト、提出課題、出席などの総合点で評価されるところが多かったと思います。
大学でも似たような感じです。
★大学の講義の成績評価方法
- 出席数
- 授業への貢献度
- 提出課題(レポートなど)
- 試験
- 教授のお気に入り
基本的には、高校と同じようにこれらの総合点で評価が決められます。
しかし高校とは少し異なる点もあります。
1個ずつ解説していきます。
出席数
説明するまでもありませんが、何回出席したかどうかで、評価が決まります。
欠席せずに毎回講義に参加していれば、出席数だけで言えば、評価はA+になるでしょう。
反対に休みすぎると出席数が足りずに、試験を受けられなくなり、失格ということになります。
基本的には、授業の3分の2を出席していれば、試験を受けることができます。
何回まで休んでいいのかなどは、後ほど詳しく説明します。
授業への貢献度
貢献度と聞くと、何か難しいことをしなければいけないのかと思うかもしれませんが、何も特別なことをする必要はありません。
貢献度というのは、参加度と言い換えることもできるかもしれません。
何をしたらいいのかというと、授業内で、いい発言をしたり、いい質問をしたりです。
別にいい発言、いい質問でなくても、普通の発言、質問でも問題ありません。
重要なのは、授業に対する積極性です。
いかに授業に入り込めるかが重要になってきます。
提出課題
こちらもわかりやすいです。
何か提出を求められたら、まずは最低限、期限までに提出する。
そしてその内容が良ければ、なおさらいい評価をもらえるでしょう。
課題と言っても色々あります。
★課題の例
- レポート
- 授業の感想
- プレゼンテーション
一番想像しやすいのが、レポートだと思います。
「授業内容をまとめて、次の授業で提出してください。」と言われたり、「講義内容について自分で調べて、まとめてきてください。」など様々なレポートがあります。
もちろん文字数も決められていることが多いです。
授業の感想は、講義の聞いて、自分の思ったこと、感じたこと、質問などを書いて提出します。
これが意外と難しい気がします。
レポートは、講義内容をまとめたりするだけです。
なので最低限、講義を聞いて、ノートを取っていれば、完成させることができます。
しかし、これは、講義内容ではなく、あくまでも講義の内容に関して、どう思うのかなど、自分の意見を書かなければなりません。
普段から何事に対しても意見を持つようにしておかないと、難しいですよね。
ここで素晴らしいことが書ければ、他の人と差別化できる気がします。
プレゼンテーションも課題の1つとカウントしました。
プレゼンテーションは、言葉の通り、みんなの前で何かを発表します。
やはりこのプレゼンテーションの内容が出来が素晴らしいと高評価をもらえます。
中学、高校でのプレゼンテーションは、多くてもクラス内で30人、40人くらいの前で行うものだったと思います。
しかし大学では、もちろん少人数のグループ内での発表もありますが、50人の前での発表、100人の前での発表と大人数の前でプレゼンテーションをしなければならない機会があるかもしれません。
そこまで多くの人の前でプレゼンテーションをしたことがある人は、学校の生徒会長だった人くらいでしょう。
ほとんどの人は、未経験なのでめちゃくちゃ緊張すると思います。
しかし、プレゼンテーションは、準備さえしっかりと行っていれば、何も怖いものなどなく、準備してきたことを出すだけです。
なので準備は十分すぎるくらいに行いましょう。
試験
試験に関しては、しっかりと勉強をしていい点数を取る。
それだけです。
試験の回数は、授業や、担当教授に代わります。
セメスターの最後に行う期末試験のみの一回限りのこともありますし、高校のように中間試験、期末試験の2回を行うところもあります。
また小テストを行い、それも成績に反映されることもあります。
この小テストが抜き打ちで行われることもあるので、常日頃から復習をしっかりと行っておきましょう。
教授のお気に入り
これに関しては、よくわからないという人もいるかもしれません。
教授のお気に入りの生徒になれば、いい評価をもらいやすくなる。
それだけのことです。
そんなことあってもいいのと思う人もいるかもしれません。
しかし、実際にあります。
高校の時も、先生と仲のいい友達が、自分よりテストの点は悪いのに、いい成績をもらっていたりしませんでしたか?
不公平感はありますが、先生、教授と仲良くなるのもその人の能力の内ですし、仲良くなっておいて損はないと思います。
例えば、試験の成績が悪かったとして、普通であれば、単位を落としてしまってもおかしくない。
ただ教授と仲良くしておいたおかげで、単位を落とさないレベルのC評価を頂けることもあるでしょう。
もちろん教授全員がそんなことをしてくれるわけではありませんが。
先輩たちのうわさだったり、教授の人柄を見て判断してみるのもいいかもしれません。
注意点
高校では、出席数、提出物、試験の点数など総合的に評価がされていたでしょう。
しかし、大学では、授業や担当教授によって何で評価するかの割合が変わってきます。
試験に比率を多く持ってくる教授もいますし、プレゼンテーションの割合を多く持ってくる教授もいます。
極端に出席数が評価の50%をくれるありがたい教授もいます。
一方で、出席点、提出課題の評価はなく、期末試験一発で評価を決める教授も中にはいます。
本当にそれぞれなので履修登録の際のシラバスをしっかりと読んだり、初回講義の際に教授の説明をよく聞くようにしましょう。
大学の講義は休むとどんな感じになる?

高校を休む際には、相当低い偏差値のところでない限り、学校に連絡を親にしてもらわなければなりませんでした。
しかし、大学では、「今日大学行くのめんどくさいな。」と思ったら、勝手に休むことができます。
なので高校と比べるとかなり簡単に休むことができます。
では実際に休むとどんな感じになるのでしょうか?
大学の講義を無断で休むとどうなる?
高校では、朝の朝礼で出席をとり、無断で休んでいた場合、朝礼後に先生から家に電話がかかってくるでしょう。
なので親にも無断で休んでいた場合、すぐにバレます。
では大学の場合はどうでしょうか?
まず大学には朝礼などありません。
なので一番初めに休んだことが発覚するのは、授業で出席を取る際です。
授業に登録している人の名簿があるので、それを教授が読み上げていき、生徒が返事をしていきます。
そして返事がない生徒がいると、声がただ小さくて聞こえなかっただけという可能性も考え、何度か名前を呼びます。
そしてその後も返事がないと、次の生徒の名前が呼ばれます。
そして出席確認が終わると何事もなかったかのように、授業が始められます。
授業終了後に、連絡がくるわけでもありません。
もう一つの休んだことが発覚するパターンは、出席カードで出欠をとる講義です。
人数が多すぎると1人ずつ名前を呼んでいくのは大変なので出席者は、出席カードに名前を書いて提出します。
なので休んだことがバレるのは、講義終了後の教授が出席カードの整理をするタイミングです。
それがいつなのかはわかりません。
講義終了直後なのか、それとも数日後なのか。
こちらも同様に連絡がくることはありません。
なので大学の講義を無断で休んでも、特に何かが起こるわけではありません。
安心して無断で休むことができます。
大学の講義は何回まで休むことができる?
無断で休んでも何も起きないからといって、休みすぎるのは危険です。
単位を落とす可能性が出てきてしまいます。
大学の講義を休んでもいい回数は決まってます。
なのでそれだけ以上休むのは単位が欲しいのであれば、やめておきましょう。
★大学の講義を休むことができる数
- 授業数の3分の1
ほとんどの大学で授業数の3分の1を休むと、単位を認定してもらえなくなります。
例えば、ある授業が15回授業があるとすると、3分の1なので5回まで休むことができます。
6回休んでしまうと、単位を落としてしまいます。
1つの授業だけでなく、複数の授業を休むと、どの授業で何回休んだのか忘れてしまう人もよくいます。
そして休みすぎて単位を落としてしまう。
このようなことが起きないように、しっかりと自分が何回休んでいるのかメモをしておきましょう。
インフルエンザなどで休む場合はどうなる?
インフルエンザや身内の不幸、教育実習などで授業を休むこともあるかもしれません。
その場合は、学校に報告をすれば、公欠、もしくは忌引としてカウントしてもらえます。
もちろんそのためには、診断書や、葬儀の日時などが記載されたものを提出しなければなりません。
なのでこのようなケースで休む際は、しっかりと証明できるものを捨てずに残しておきましょう。
証明できるものがないと、無駄に休みがカウントされてしまい、1日休みを損してしまいます。
大学の講義をサボる方法を伝授

あまりよろしいことではないですが、大学の講義をサボりたくなることはどんな人でも必ずあるでしょう。
サボるはサボるでもいろいろ種類があると思います。
★大学の講義のサボる例
- 欠席
- 途中退席
- 出席するがよそ事をする
大学の講義をサボることはできるのか?
サボると言えば「欠席する」、「途中退席する」、「出席するがよそ事をする」、この3つが思い浮かびますが、結論から言ってサボることはできます。
他にもサボるタイプがあればコメントで教えてください。
特に受講人数が多ければ多いほど簡単にサボることができます。
人数が多ければ、先生からもバレる可能性も少ないですし、後ろの方の席を確保できればもはや先生からは見えません。
欠席してサボる方法
これまでの内容を読んでくださった方は、方法もクソもないということが理解できているでしょう。
改めて言いますが、高校と違い、大学の講義は自由に休むことができ、大学から連絡がくることもありません。
なのでサボりたかったら何もせずに欠席してください。
または、出席カードで出席を取るタイプの講義の場合、友達に代わりに出席カードを書いてもらえば、欠席でも出席扱いになることができます。
バレたらヤバいですけどね。
途中退席してサボる方法
こちらは欠席するよりも少し難易度が上がります。
しかし、やるべきことはシンプルです。
★途中退席してサボるためにすること
- 嘘をつく
嘘は良くないことですが、サボるためには手段を選んでいてはいけません。
2パターン紹介していきます。
1つ目のパターンは、先に途中退席することを伝えておく方法です。
先に伝えておくことで、堂々と教室を出ることができます。
あらかじめ遊びに行く予定がある場合、「遊びに行くので途中退席します。」と堂々といって許されることはないでしょう。
しかし、誰かのお見舞いに行ったり、学年や時期によっては、就活面接に行ったり、会社説明会や、インターンシップに行くなら全然OKだと思います。
2つ目のパターンは、いきなり途中退室しますと伝える方法です。
こちらは、事前に伝えておくよりも難易度は高めです。
急に友達と遊ぶ予定ができた時に使うことができます。
急に途中退席しなければならないのは、余程の理由がない限りないですよね。
なので「体調が悪くなった」と伝えるのが一番信じてもらえるでしょう。
その場合は、少しばかりの演技も必要です。
それができない人は、先に伝えておくパターンの誰かのお見舞いや、就活などの理由を伝えるのも最悪いいでしょう。
その場合、「今度からは先に伝えておいてね。」など色々やりとりがあるとは思います。
そして、そのやりとりの間、教室中の視線が集まります。
しかし退室できないことはないでしょう。
出席をするがよそ事をしてサボる方法
こちらは、中学、高校と経験したことがある人もいるのではないでしょうか?
なので割と皆さんサボるのがうまいのではないでしょうか?
★よそ事をしてサボる際のポイント
- 後ろの方の座席を確保する
後ろの方の座席を確保するのが、一番バレずにサボることができます。
後ろの方だと、前からは何をしているかよく見えませんし、前に座っている人たちの影に隠れることもできます。
高校の時は、座る座席が指定されていましたが、大学では自由です。
なので座席は早い者勝ちです。
後ろの方の座席はやはり人気なので、前の授業が終わったらすぐに次の教室に向かって座席を確保する。
または、前の授業がなく、空きコマの友達に座席を確保しておいてもらう。
それができれば、あとはうまくやるだけです。
もちろん後ろの方の座席でなくてもサボることはできますが、後ろに行けば行くほど、バレるリスクは低くなります。
大学の講義をサボる際の注意点
いくらサボれるからと言っても注意すべきことはあります。
1つ目が欠席するときです。
大人数での講義なら出席を出席カードで取ることがあるかもしれません。
先ほども説明しましたが、代わりに友達に自分の分も書いてもらえたら、欠席しても出席になることができます。
それが講義をただ聞いているだけ形式であれば、何の問題もないですが、生徒参加形式の場合、自分が当てられる可能性があります。
当てられても自分がいなかったら大問題ですし、友達に出席カードを書いてもらったとバレたらならば、友達にも迷惑をかけてしまうので気をつけましょう。
2つ目が講義中によそ事をするときです。
よそ事でスマホをいじるというのが多いと思いますが、講義中に先生が座席をグルグル回って後ろの方まで回りながら講義をすることがあります。
その時に後ろの方に座っているから安心しきってスマホゲームに集中しすぎて、先生が回ってきたときも気づかずにやり続けて、先生にバレて怒られるという人を見たことがあります。
なので出席しながらサボる場合は、どんなイレギュラーが起きてもいいように意識を少しは授業の方に向けておきましょう。
まとめ
大学の講義がどんな感じか紹介してきました。
大学によって違いはあると思いますが、だいたいが先生の話を聞くだけの講義か、生徒が参加をする講義だと思います。
あまりおすすめはしませんが、一応講義をサボることもできます。
なので適度にサボって気分転換をするのもいいかもしれません。
ただサボりすぎると単位を落とすしてしまうかもしれないのでそこは注意しましょう。
ちなみに大学4年生にもなると講義をサボるとか以前に授業がほとんどありません。
こちらの文系大学4年生の授業数は?時間割スケジュールを大公開!で大学4年生がどんな生活をしているのか解説しているので気になる方はご覧ください。
この記事を読んでいただいた人の中で、1人でも大学の講義がどんな感じなのか、休むとどんな感じになるのか、サボることはできるのか、そんなことの参考になった人がいれば、うれしいです。
これで、終わります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。